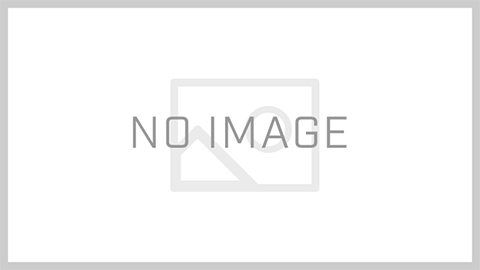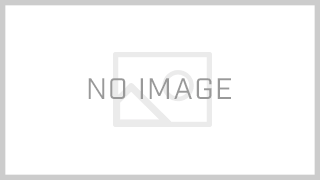奈良の東大寺は、その壮大な大仏で知られ、多くの観光客が訪れる名所です。
しかし、大仏殿内には、ただ大仏を見るだけではない魅力が隠されています。それは「柱くぐり」というユニークな体験です。
この記事では、大仏様の鼻の穴と柱くぐりの不思議な関連性について探ります。
大仏様の鼻の穴の大きさ
まずは、大仏様自身の鼻の穴から見ていきましょう。
大仏様の鼻の穴は、縦37センチ、横30センチ、奥行き120センチというサイズで、意外にも長方形に近い形をしています。
この大きさは、大人の頭部がすっぽりと収まるサイズであり、その大きさには訪れる人々を驚かせます。
柱くぐりの伝統
大仏殿内のある特定の木の柱には、底部に人工的に開けられた穴があります。
この穴は、大仏様の鼻の穴と同じサイズで、多くの訪問者がくぐることで知られています。
特に子供たちに人気で、穴をくぐることが「知恵が身につく」「無病息災」などのご利益があるとされていますが、その起源は非常に興味深いものです。
穴の起源と文化的意味
この穴は、もともと邪気を避けるために開けられたもので、柱の位置が鬼門(北東方向)に当たるためです。
陰陽道の考え方に基づき、邪気が柱にぶつかり散乱するのを防ぐために穴が開けられました。
しかし、時が経つにつれて、この穴がさまざまなご利益を持つという話が広まり、今日では多くの人がそのご利益を信じて柱くぐりを行います。
現代における柱くぐりの意味
「信じる者は救われる」という言葉が示すように、柱くぐりは多くの人々にとって精神的な平安をもたらす行為となっています。
訪問者はこの伝統的な行為を通じて、何かしらの精神的な支えや希望を見出すことができるのです。
訪れる際のヒント
東大寺を訪れる際は、大仏だけでなくこのユニークな柱くぐり体験もお楽しみください。
特に週末や祝日は混雑が予想されるので、朝早めの訪問がおすすめです。
また、柱くぐりは小さな子どもから大人まで幅広い年齢の人が楽しめますが、大人の場合は体型を考慮して挑戦してください。
参考サイト
・東大寺