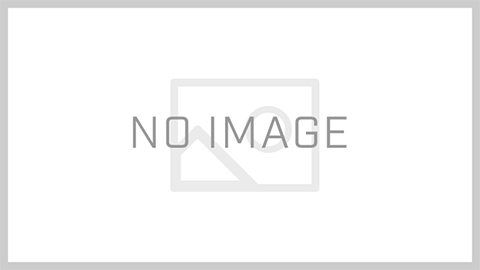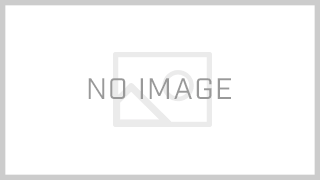福沢諭吉(1835-1901)は、日本の教育者、思想家、そして明治時代の近代化の先駆者として知られています。彼の名言「天は人の上に人を作らず」は、多くの人々に親しまれていますが、その背後には興味深い物語が隠されています。
 福沢諭吉<1835年-1901年>
福沢諭吉<1835年-1901年>娘の恋愛との関連
福沢諭吉は厳格な教育者であり、娘の恋愛にも厳しい目を向けていました。彼の娘が身分違いの男性と交際していることを知った際、彼は怒り、二人を別れさせました。
このエピソードは、「天は人の上に人を作らず」という言葉にどのように関連しているのでしょうか?
福沢諭吉は、自身の理念に忠実であり、社会的な階層や身分に厳格な考えを持っていました。彼は、娘の恋愛においても、この信念を貫いたのです。
しかし、同時に、彼の言葉が人々の平等を強調するものとして広まっていったことは興味深い偶然です。
言葉の意味と広がり
「天は人の上に人を作らず」という言葉は、一般的には人々の平等を強調するものとして知られています。しかし、福沢諭吉自身の行動と矛盾する側面もあります。
彼は娘の恋愛に厳格であった一方で、この言葉は社会的な階層にとらわれない人々の平等を訴えるものでもあります。
この言葉の意味や広がりについて考察することで、私たちは福沢諭吉の思想や人間性に迫ることができるでしょう。
天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずは本来
「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」には本来続きがあります。
「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずといへり。
~中略~
されども今廣く此人間世界を見渡すにかしこき人ありおろかなる人あり貧しきもあり冨めるもあり貴人もあり下人もありて其有様雲と坭との相違あるに似たるは何ぞや。」
要約すると、『神は人々を平等に作ったけど、それでも不平等、差別が起きるのは学問をおさめているかである』と本来、福沢諭吉は学問のススメの中で伝えたかったのではないかと思います。
結論
福沢諭吉の言葉は、単なる格言以上の意味を持っています。
その背後には人間ドラマが隠されており、私たちに考えさせるものがあります。彼の逸話は、単なる歴史の一部ではなく、私たちの日常にも影響を与えていることを忘れないでください。