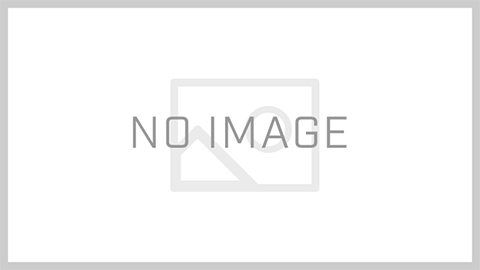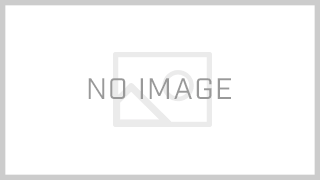奈良と言えば、その象徴とも言えるのが自由に町を闊歩する鹿たちです。秋の発情期にはその角が特に危険を伴うため、「鹿の角きり」という伝統行事が春日大社で行われています。
この行事はなんと江戸時代から約340年も続いているのです。
そう考えると、鹿が奈良にいたのはかなり昔からのことであり、その起源は意外にも遠く、関東地方の茨城県にある鹿島神宮に遡ります。
鹿島神宮と奈良の鹿
鹿島神宮は、茨城県鹿嶋市に位置し、日本古来からの信仰を集める場所です。
この地域のシンボルでもある鹿は、地元サッカークラブ「鹿島アントラーズ」のエンブレムにもなっており、その名前やマスコットキャラクター「しかお」も鹿をモチーフにしています。
さらに、鹿島神宮自体が鹿と深い関係を持っていることから、「鹿づくし」とも言える文化が育まれています。
奈良に渡った白鹿の伝説
伝説によると、767年に奈良に春日大社が建立された際、鹿島神宮の神様を勧進するために、神様が白鹿に乗って鹿島から奈良へとやって来たと言われています。
これが奈良の鹿の起源であるとされ、その鹿の末裔たちは今も奈良公園で訪れる人々に鹿せんべいをねだりながら、親しまれています。
春日大社と鹿島神宮の結びつき
春日大社は藤原氏の氏神を祀る神社であり、奈良における最も重要な神社の一つです。
神社は鹿島神・タケミカヅチノミコトをはじめ、フツヌシ、アメノコヤネノミコト、ヒメガミの4柱の神様を祀っており、これらはすべて武神としての側面を持っています。
この神々が奈良の地にもたらされたことで、春日大社はその信仰の中心となりました。
日本の武神としての鹿島神宮
鹿島神宮は、タケミカヅチノミコトを主神として祀る神社で、その神は武道や武士にも影響を与えています。
実際、多くの道場や武道場には鹿島大明神や香取大明神の掛軸が飾られており、その信仰は今も受け継がれています。
まとめ
奈良の鹿の背景には、ただ単に野生の鹿がいるわけではなく、古くからの信仰や伝説、文化的なつながりが存在します。
鹿島神宮から始まるこの物語は、奈良の鹿をただ見るだけではなく、その歴史や文化を知るきっかけとなるでしょう。次に奈良を訪れる際には、これらの鹿たちを新たな視点で見ることができるかもしれませんね。